人口が6千人にも満たない小さな町ですが、ここには都会では味わえない静けさがあります。
しかし、最近SNSや動画サイトなどで「北海道にも巨大地震が来る」という噂が繰り返し目に入ってくるようになりました。一部では都市伝説だとも言われていますが、無視して良い話ではありません。
2018年に発生した北海道胆振東部地震では、全道が停電となる「ブラックアウト」という大きな被害を経験しました。噂や予言がどうであれ、実際に自然災害は起こっており、今後も起こらないとは言い切れません。
だからこそ、私たちにできることは「備える」ことです。

特に田舎では、救援が来るまでに時間がかかる場合もあります。周囲にコンビニや電気店が少なく、公共交通も整っていない地域では、災害時の“自助”が命綱になることもあるのです。
停電や断水に備えて、最低限の食料や水、そして情報を得るための手段を確保しておくことは大切です。
私は、災害時に使えるポータブル電源やラジオ付きのライトなどを見直しています。
最近では、1万円台から購入できる小型ポータブル電源も増え、スマホの充電やLEDライトの点灯、小型の電気毛布を使うのにも十分な電力を確保できます。
日頃からキャンプ用品としても活用できるため、無駄にはなりません。
また、水の備蓄に関しても、2Lペットボトルを複数ストックしておくと安心です。大人1人あたり1日3Lを目安に、最低でも3日分、できれば7日分の水を確保しておくことが推奨されています。
噂に流されすぎるのも考えものですが、何も備えていないのはもっと危険です。
「何も起きなかった」ではなく、「何も起きなかったけど備えていてよかった」と思える未来をつくりたいですね。
まとめ
また、北海道というと「雪国で安全」というイメージが根強いですが、地震や大雨による被害は実際に起きています。2018年の胆振東部地震を覚えている方も多いと思いますが、あの時も広範囲で停電が発生し、電気・水道・ガスが一時的に止まりました。寒冷地でのライフライン喪失は、命に関わる問題です。
特に冬場の停電は暖房が使えなくなるため、非常用の電源やカセットコンロ、毛布などの備えは欠かせません。また、夏場でも近年は猛暑が続いており、エアコンが使えない状況は高齢者や子どもにとって深刻なリスクになります。
最近では、防災グッズも進化しており、ポータブル電源やソーラーライト、簡易トイレなども手に入りやすくなっています。価格も手頃なものが増えているので、「まだ何も備えていない」という方は、最低限のグッズだけでも揃えておくことをおすすめします。
そして、備えるだけでなく、それを定期的に見直すことも大切です。賞味期限のある保存食や、使用期限のある電池など、チェックしておかないと「いざという時に使えなかった」ということにもなりかねません。
防災は一度きりの準備ではなく、「続ける意識」が何より大事です。災害は予告なしにやってきます。だからこそ、“今”がその一歩を踏み出すチャンスかもしれません。
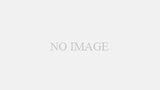

コメント